この記事は7分で読めます。
こんにちは。
今回は、高齢者を中心にトラブルが急増している「リースバック契約」についてお話しします。
持ち家を売っても住み続けられる仕組みとして注目されていますが、便利さの裏には数々のリスクが潜んでいます。
この記事では、よくある問題点と安全に活用するためのポイントをわかりやすくまとめます。
そもそもリースバックって何?
リースバックとは、現在住んでいる自宅を不動産業者などに売却し、そのまま家賃を払って住み続ける仕組みです。
現金が手元に入るうえ、住み慣れた家を出なくて済むため、老後の資金確保として注目されがちです。
しかし…6つの大きなリスクに要注意!(この相談が増えてきました。)
① 売却価格が相場より安すぎる
通常の売却では得られるはずの価格より2〜3割安い金額で売却されるケースが多く、資産価値が大きく目減りしてしまいます。
② 賃料が相場より高い
売却後の賃料が相場より高く設定されていることが多く、家計を圧迫する原因になります。さらに契約更新時に家賃が上がるケースも。
③ 「ずっと住める」とは限らない
多くのリースバック契約が「定期借家契約」であるため、数年で退去しなければならない可能性があります。
再契約も保証されていません。
④ 所有者が変わるリスク
購入した不動産会社が物件を転売した場合、新たな所有者が契約条件を変えたり、退去を求めてくるリスクがあります。
⑤ 押し売りや執拗な勧誘
長時間の説明や「今だけのチャンス」といった営業トークで契約を急がせるケースも多く、冷静な判断ができなくなる恐れがあります。
⑥ 解約時の高額な違約金
途中で契約解除しようとすると、高額な違約金を請求されるトラブルも多く報告されています。

高齢者を狙った悪質商法が社会問題に(トラブル件数急増!)
消費生活センターには「認知症の親が勝手に契約していた」「契約書の内容がわかりづらかった」などの相談が多数寄せられています。
特に高齢の一人暮らし世帯が狙われやすくなっています。
トラブルを避けるためにやるべきこと
- 契約前に必ず複数の不動産会社から見積もりをとる
- 「普通借家契約」か「定期借家契約」かを必ず確認する
- 契約書をすべて読み込み、分からない言葉は調べるか相談
- その場で即決せず、家族や法律専門家に相談する
- 高齢者一人で判断せず、周囲の協力を得る
まとめ|便利な制度にも「落とし穴」がある
リースバックは、資金確保と住み続けたいニーズを叶える一方で、「安く売られて高く住まされる」「突然追い出される」「契約の意味がよく分からないまま進められる」など、重大なリスクを含んでいます。
特に高齢の家族が関わる場合は、契約前に家族や弁護士、消費生活センターなどに相談して慎重に判断することが大切です。
安易な契約が将来の不安や損失につながらないよう、しっかり情報を集めて行動しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
あなたやご家族の安心な暮らしのためにも、冷静な判断と事前の準備を忘れずに。
また明日!
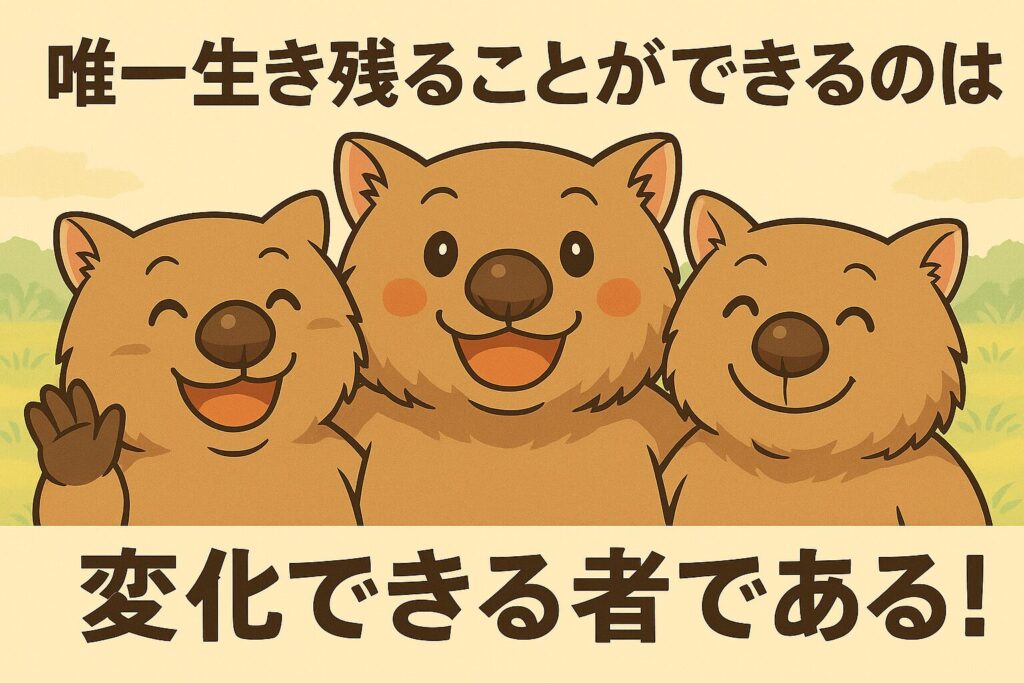


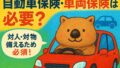
コメント