この記事は7分で読めます。
「会社で年末調整を受けたから、確定申告はいらないよね?」 そう思っている会社員・公務員の方は多いですが、実はケースによっては申告が必要なことがあります。
今回は、2025年最新情報に基づき、年末調整と確定申告の違いや注意点をわかりやすく解説します。
年末調整とは?
年末調整は、会社や役所など勤務先が代わりに税金の精算をしてくれる手続きです。
毎月の給与から引かれている所得税は「概算」で計算されており、年末に実際の所得と控除額を基に「払いすぎ」や「不足分」を調整します。
- 対象者:原則、給与所得者(会社員・公務員)
- 実施時期:毎年11月〜12月
- 提出書類例:扶養控除等申告書・保険料控除申告書など
- 特徴:勤務先が代行するため、通常は自分で税務署へ行く必要なし
会社員や公務員の多くは、この年末調整だけで所得税の計算が完結します。
確定申告とは?
確定申告は、1年間の収入や控除を自分で計算し、税務署に申告する手続きです。
会社員・公務員であっても、次のような場合は確定申告が必要です。
- 副業や不動産収入など、給与以外の所得が年間20万円を超える場合
- 2か所以上から給与を受けており、主たる勤務先以外の給与収入が20万円を超える場合
- 医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税など)・住宅ローン控除(初回)を受けたい場合
- 年の途中で転職し、前職の源泉徴収票が年末調整に反映されていない場合
- 年間の給与収入が2,000万円を超える場合
申告期間:毎年2月16日〜3月15日 この期間内に、税務署やe-Taxで手続きを行います。
年末調整と確定申告の違いを比較
会社員・公務員にとって最も混乱しやすいポイントがここです。
違いをわかりやすく表にまとめました。
| 項目 | 年末調整 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 手続きする人 | 勤務先(会社・役所) | 納税者本人 |
| 対象者 | 給与所得者(副業なし、または副収入20万円以下) | 副業あり・高額医療費・不動産収入などがある人 |
| 実施時期 | 毎年11月〜12月 | 翌年2月16日〜3月15日 |
| できること | 扶養控除、保険料控除などの調整 | 医療費控除、寄附金控除、住宅ローン控除(初回)など幅広い控除 |
| 目的 | 年間の税額を自動で精算 | 1年分の収入・控除をすべて計算し税額を確定 |
簡単に言うと、年末調整=会社がやってくれる手続き、 確定申告=自分でやる手続きです。
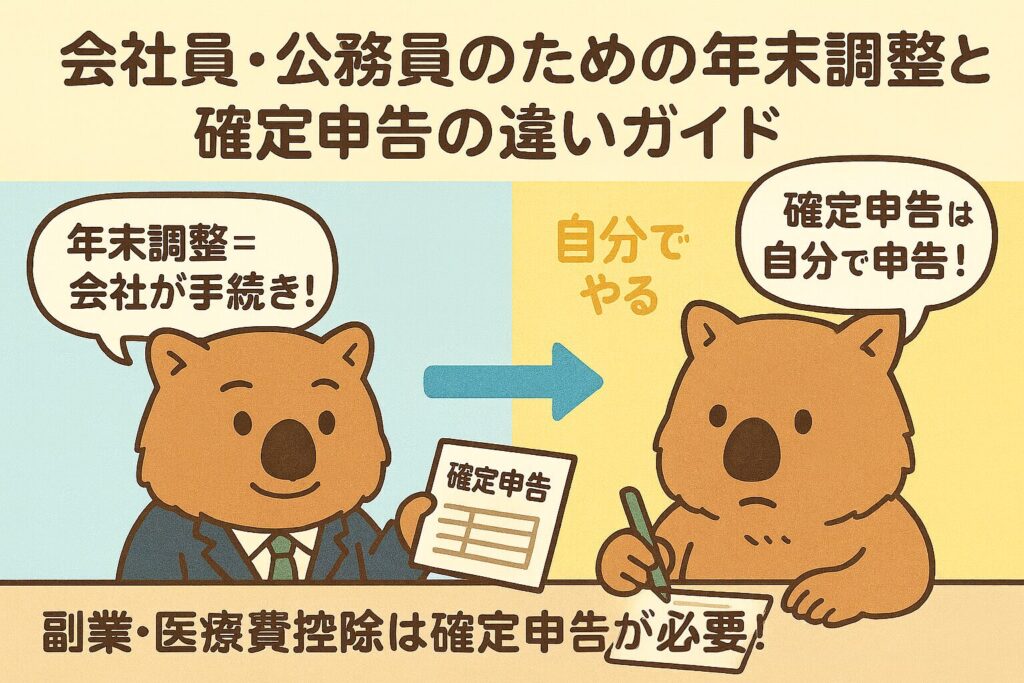
会社員・公務員が確定申告をした方がいいケース
実は、条件に当てはまらなくても、確定申告をすることで得をする場合があります。
- ふるさと納税をして、ワンストップ特例を利用しなかった場合
- 医療費が多くかかった年で、還付金が受け取れるケース
- 株式や投資信託で損失が出た場合、損益通算や繰越控除で税金が戻る可能性がある
「うちは会社員だから関係ない」と思っていても、節税のチャンスを逃している人は意外と多いです。
まとめ|年末調整と確定申告を正しく使い分けよう
会社員・公務員は原則、年末調整で所得税が完結しますが、 副業収入や医療費控除など条件次第で確定申告が必要になるケースがあります。
特に最近は副業解禁やふるさと納税の普及で、申告が必要な人は年々増えています。
年末調整と確定申告の違いを知っておけば、余計な税金を払わずに済む可能性があります。
まずは自分がどちらに当てはまるのかをチェックしておきましょう。
特に部活顧問の中には、自治体の派遣社員「休日の部活動指導員」として通常よりも高い給与をもらっている方もいるようです。教えてあげてくださいね!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
またお会いしましょう!

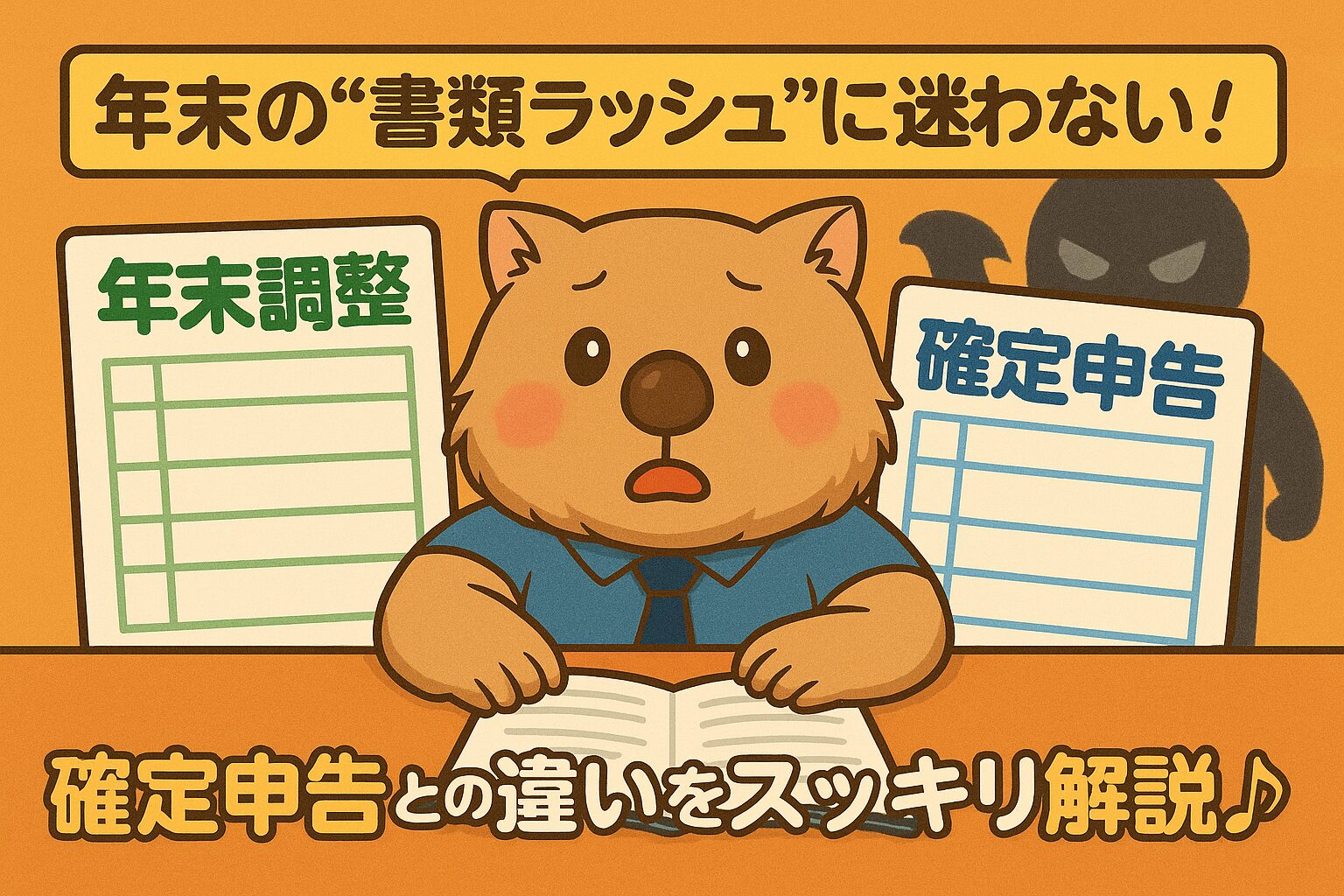


コメント