この記事は6分で読めます。
iDeCoと生命保険料控除、どちらも「節税できる制度」として知られていますが、控除の種類・金額・計算方法には大きな違いがあります。
この記事では、2025年最新の制度に基づいて、iDeCoと生命保険料控除の違いをわかりやすく解説します。
iDeCo(個人型確定拠出年金)の税額控除
iDeCoの掛金は、全額が「所得控除」の対象です。
つまり、拠出した金額の分だけ課税所得が減少し、所得税と住民税の両方が軽減されます。
節税額の計算式:
掛金 ×(所得税率+住民税率)
例:
年収500万円の会社員が、年間14.4万円を拠出した場合
→ 所得税10%+住民税10% = 合計20%
→ 節税額=14.4万円 × 20% = 28,800円の節税
- 課税所得が高い人ほど、節税効果が大きくなります。
- 掛金の上限は職業・年金制度によって異なります(例:2025年の会社員は年間最大27.6万円)。
生命保険料控除(一般生命保険)
生命保険の控除も所得控除ですが、控除額には明確な上限があり、段階的な計算式が適用されます。
| 年間保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 払込金額全額 |
| 20,001円~40,000円 | (保険料×1/2)+10,000円 |
| 40,001円~80,000円 | (保険料×1/4)+20,000円 |
| 80,001円以上 | 一律40,000円 |
※一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険のそれぞれに同様のルールがあり、合計最大12万円が所得控除されます。
例:
年間8万円の保険料を支払っても、控除額は上限の4万円となり、それ以上の支払いは控除額に反映されません。

iDeCoと生命保険料控除の違いまとめ
| 項目 | iDeCo | 生命保険料控除 |
|---|---|---|
| 控除の種類 | 掛金全額が所得控除 | 払込保険料に応じて段階的控除 |
| 計算方式 | 掛金 ×(所得税率+住民税率) | 所定の式に基づき最大4万円(1項目) |
| 控除の上限 | 年収・職業等によって異なる(例:27.6万円) | 各4万円×3種類=最大12万円 |
| 節税効果 | 高所得者ほど大きい | 支払額が多くても上限以上は控除不可 |
まとめ:控除の仕組みを理解して節税に活かそう
- iDeCoは掛金全額が控除対象。高所得者には特に有効。
- 生命保険料控除は段階的な計算式と明確な上限あり。
- 両方とも「所得控除」だが、仕組みも効果も大きく異なる。
「どれくらい節税になるのか?」を知ることは、賢い家計管理への第一歩。
iDeCoと保険控除、それぞれの特徴を理解して、節税にうまく活かしましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
また明日!

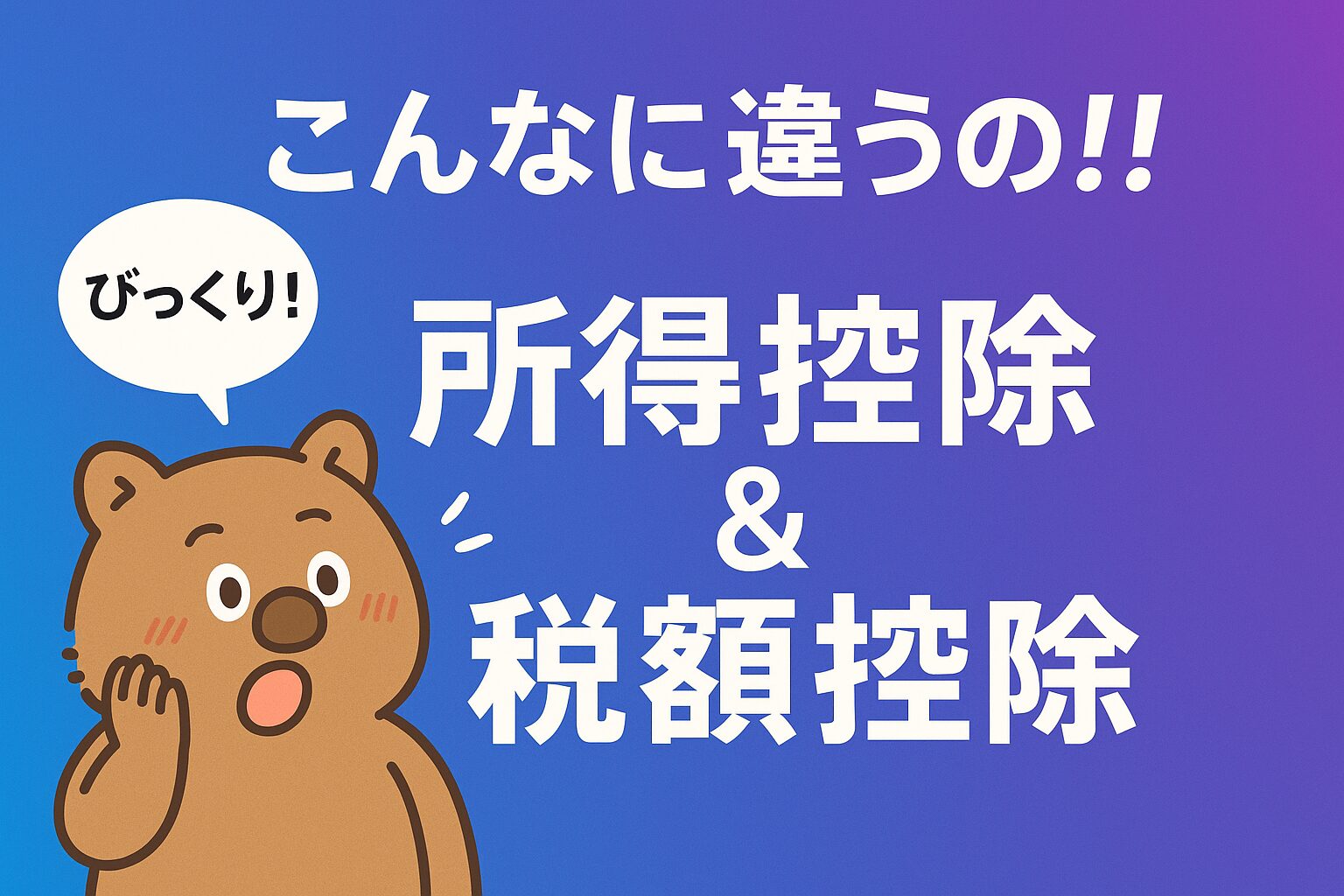


コメント